生産性指標がない会社・工場は、下記のようになる。
| ①「目標」と「評価」のない職場になる |
| ②生産結果が、OKかNGか、わからない |
| ③問題が顕在化しない、問題が放置される |
| ④仕事における、嬉しい・悔しい、やりがいが生まれにくい |
| ⑤仲間と目指す目標がない、一致団結しにくい |
1時間当たりの限界利益、1時間当たりの生産数量などの中から、
算出が簡単で、みんなが理解しやすい指標を設定すればOK.
グラフ化すれば、絶対値と傾向が一目でわかる。
数値で勝負!(明るく、前向き)、
経営に、絶対必要である。
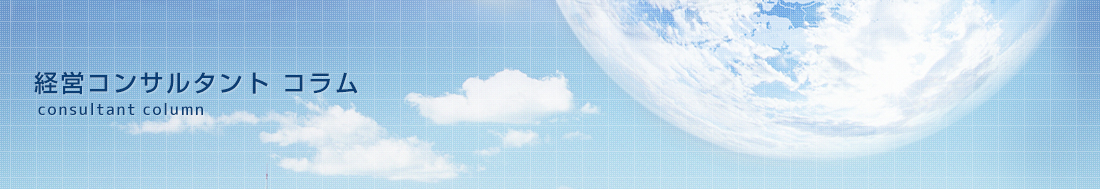
生産性指標がない会社・工場は、下記のようになる。
| ①「目標」と「評価」のない職場になる |
| ②生産結果が、OKかNGか、わからない |
| ③問題が顕在化しない、問題が放置される |
| ④仕事における、嬉しい・悔しい、やりがいが生まれにくい |
| ⑤仲間と目指す目標がない、一致団結しにくい |
1時間当たりの限界利益、1時間当たりの生産数量などの中から、
算出が簡単で、みんなが理解しやすい指標を設定すればOK.
グラフ化すれば、絶対値と傾向が一目でわかる。
数値で勝負!(明るく、前向き)、
経営に、絶対必要である。
評価制度で、社員の行動の中身を改善する。
行動が変われば、仕事の結果が変わる。
そのためにやることは、下記の通り。
①求める結果を明確にする
②会社が求める行動を明確にする
③①②を評価制度に落とし込む
④評価結果が報われるようにする
①~④で、下記をつくり出す。
(1)成果へのこだわり
(2)やりがい
(3)自信とプライド
(4)悔しさ
(5)適度な緊張感
わかりやすくて、よい仕組みをつくって、
正しく運用すれば、社員の行動は大きく変わる。
業績が落ちる要因は、下記である。
1 ニーズが変わる
2 ライバルが力をつける
3 ミスをする
今回は、「ミス」について、記す。
ミスは、様々なダメージ・損失・損害を生み出す
●顧客に損害を与える、迷惑をかける
●顧客の信頼を失う
●金額損失が発生する
●組織が混乱する
●精神的ダメージがある
ミス要因は、経営側(管理側)にあるケースがほとんどである。
現場の人を追及し、責めるアプローチでは、ミスは減らない。
下記は、経営側(管理側)のミス要因。
①マニュアル(作業方法資料)の不備
②指示のやり方の不備
③人の配置の不備
④5Sの不備・・・ごちゃごちゃ、探し、迷い、間違い
⑤設備・機械の不備
⑥道具の不備
⑦レイアウトの不備・・・狭い、広い、低い、高い
⑧過度な負荷(仕事量)
⑨不適正な作業条件・・・規格、精度、スピード、緊張
⑩能力・体力の不足
⑪教育の不足
⑫意欲の不足
ミスを抑える力は、企業力の重要な構成要素となる。
攻めも大事だが、守りも大事である。
随分前にある企業の企業再生に取り組んだ。
練りに練った戦略とアクションプランで、
社員のみんなは、どんどん行動した。
そして、確かな利益を生み出した。
1 製品群別競争戦略の策定と実行
2 業界・ライバル・チャネル・自社の情報活用システムの構築
3 商品開発・研究開発体制の抜本的見直し
4 営業本部の有益性向上と営業ライン力の強化
5 品質による競争優位性の発揮
6 安定供給を実現できる調達戦略の策定と実行
(1)工場の再編
(2)調達リードタイムの短縮
(3)メイン工場の競争力強化
7 在庫圧縮によるキャッシュフロー改善
8 物流諸問題のスピーディーな改善
9 徹底した全社トータルコストの低減
10 全社におけるR(リサーチ)-PDCAシステムの構築
戦略キーワードは、下記の通り。
①独自の競争戦略 ②No.1製品づくりへの挑戦
③コストダウンの徹底 ④スピードマネジメントの実践
⑤コア・コンピタンスの確立→競争優位性発揮
今でも、ど真ん中で使える「フレームワーク」である。
低収益に苦しんでいる、ある製造業。
その理由は、下記。
①損益分岐点売上が上がっている
利益が出にくくなっている
②①の理由
●限界利益率の低下
●固定費の圧縮遅れ
③売価設定原価より発生原価が高い
●変動費の超過
●レート設定の不備
●稼働率低下で発生レート高騰
●作業時間の短縮の遅れ
●損失・間接・価値の3区分管理の不備
④顧客別損益、工程別損益、製品別損益が、わかっていない
これがわからなければ、具体的対策の打ちようがない
マネジメントと現場のダブルアプローチでの、
経営改革が急務である。
新型コロナの影響で、経営活動における制約・障害はあるが、
企業としては、今できることにベストを尽くすしかない。
社員一人一人のパフォーマンス(行動・成果・効率)を、
落とさないことが重要である。
「今、できることは何か」、「今、やることは何か」を、
具体化して、確実に遂行する。
営業・技術・製造・品質・管理での課題は、
たくさんあるはずである。
危機感を有して、企業としての成長を図ることが、
最大のリスク回避となる。
ある営業課長とのやり取り・・・。
私「一日の中で、営業活動の時間は何%ぐらいですか?」
課長「50%以上はあると思います」
簡単な分析をしてみると、30%もなかった。
30%を40%にするだけで、営業量は133%になる。
下記を明確にして実行するだけで、営業量は確実に増える。
①受注・売上アップのために増やしたい仕事
②時間を短縮したい仕事と減らし方
営業量と営業成果は比例する。
管理職で、チームの成果が決まる。
管理職には、5つの顔がある。
①リーダーとしての顔
②仕事のプロとしての顔
③部下の上司としての顔
④上司のパートナーとしての顔
⑤R(リサーチ)-PDCA責任者としての顔
①~⑤のバランスと、合計点の高さが重要である。
セルフチェックからの、やること決定、実行、継続、工夫で、
管理職のプラスの影響力は、大きく高まる。
生産性20%アップで、17%
減の作業時間短縮が実現する。赤字企業、赤字になりそうな企業の、
お手伝いをさせていただく機会が多い。
そんな時、損益分岐点売上を下げるコンサルを徹底する。
たとえば、
①固定費 100億円 → 98億円 2億円圧縮
②限界利益率 50.0% → 53.5% 3.5P改善
③損益分岐点 200億円 → 183億円 17億円ダウン
改善前、売上200億円で、とんとん(黒字ゼロ)だったのが、
改善後、売上200億円で、9億円の利益になる。
損益分岐点売上は、低いほど利益が出やすい。
利益が出やすい収益構造に変える。
損益分岐点売上は、わかりやすく、簡単な指標である。
赤字企業、赤字になりそうな企業は、
重要な経営課題の一つとして、
「損益分岐点売上を下げる」に着手することを、
おすすめする。